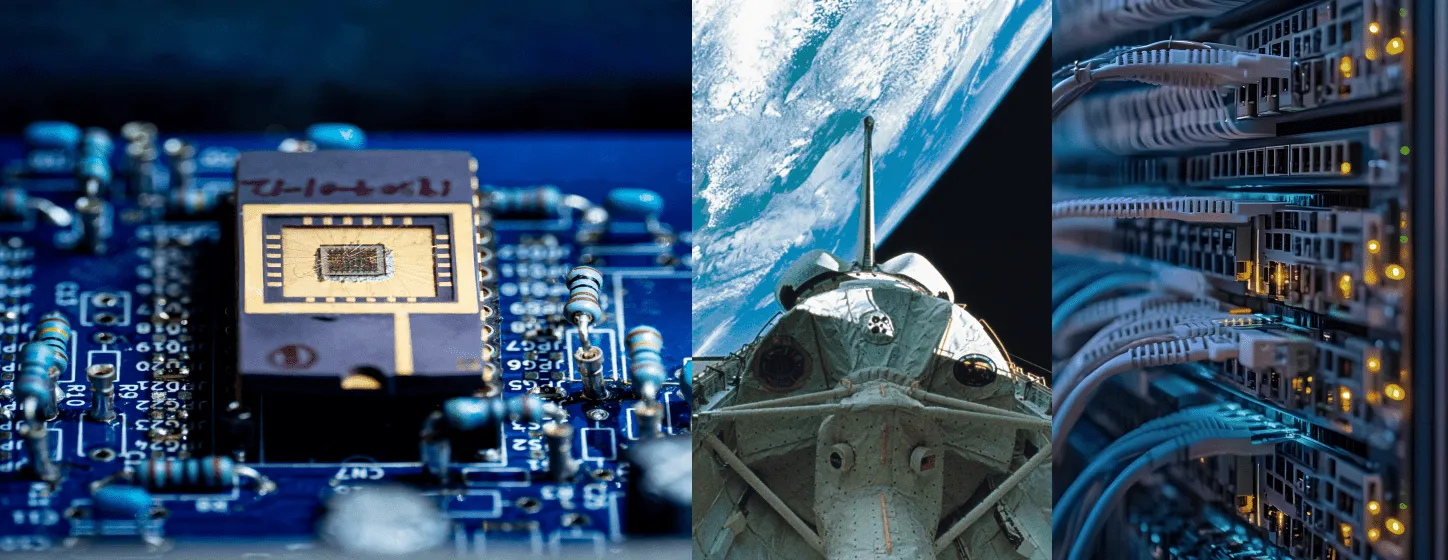BRAND STORY
なぜ今ダイヤモンド半導体か?
人類が待ち望んだ
「究極の半導体」
その高い性能から、「究極の半導体」と呼ばれるダイヤモンド半導体。その特性は、近年の社会課題である原子力関係や宇宙産業、通信産業が近年直面する課題解決に有用。本格的に実用化すれば通信衛星や基地局、EVなど、さまざまな分野で普及することは間違いない。
1980s~
ダイヤモンド半導体研究の歴史について
未来のため、一歩ずつ前進してきた研究
こうした特性に着目した研究者の間で1980年代からダイヤモンド半導体の研究が行われてきたが、技術的課題に加えて、この特性を活かせるマーケットが当時なかったことから、社会実装にまで至ってはいなかった。
そもそもダイヤモンド半導体研究の起点は、1982年に日本の旧無機材質研究所(現NIMS)が、世界初の気相合成法を成功させたことにある。気相合成法(CVD)とは、気相の化学反応によって固体を析出させる方法であり、炭素を含むメタンガスと水素ガスを原料として合成ダイヤモンドを作り出す技術だ。
世界中で研究が進む中、日本ではNIMSや国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)など様々な研究所が研究開発を行ってきた。ダイヤモンド半導体の可能性を信じる研究者たちがこれまでに着実な一歩を推し進めてきたことには変わりないが、当時はあくまで要素技術の研究であり、その目的も様々。実用化にはまだ長い道のりが存在した。
そんな状況を大きく変える契機となったのが、2011年3月11日の東日本大震災である。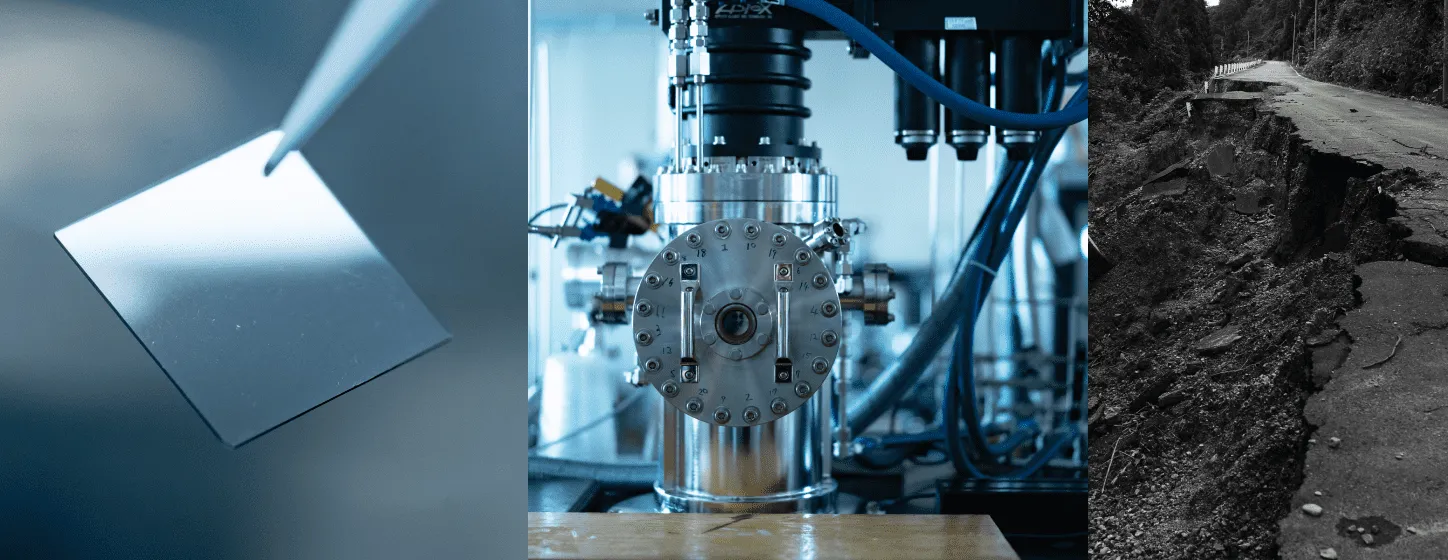
そもそもダイヤモンド半導体研究の起点は、1982年に日本の旧無機材質研究所(現NIMS)が、世界初の気相合成法を成功させたことにある。気相合成法(CVD)とは、気相の化学反応によって固体を析出させる方法であり、炭素を含むメタンガスと水素ガスを原料として合成ダイヤモンドを作り出す技術だ。
世界中で研究が進む中、日本ではNIMSや国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)など様々な研究所が研究開発を行ってきた。ダイヤモンド半導体の可能性を信じる研究者たちがこれまでに着実な一歩を推し進めてきたことには変わりないが、当時はあくまで要素技術の研究であり、その目的も様々。実用化にはまだ長い道のりが存在した。
そんな状況を大きく変える契機となったのが、2011年3月11日の東日本大震災である。
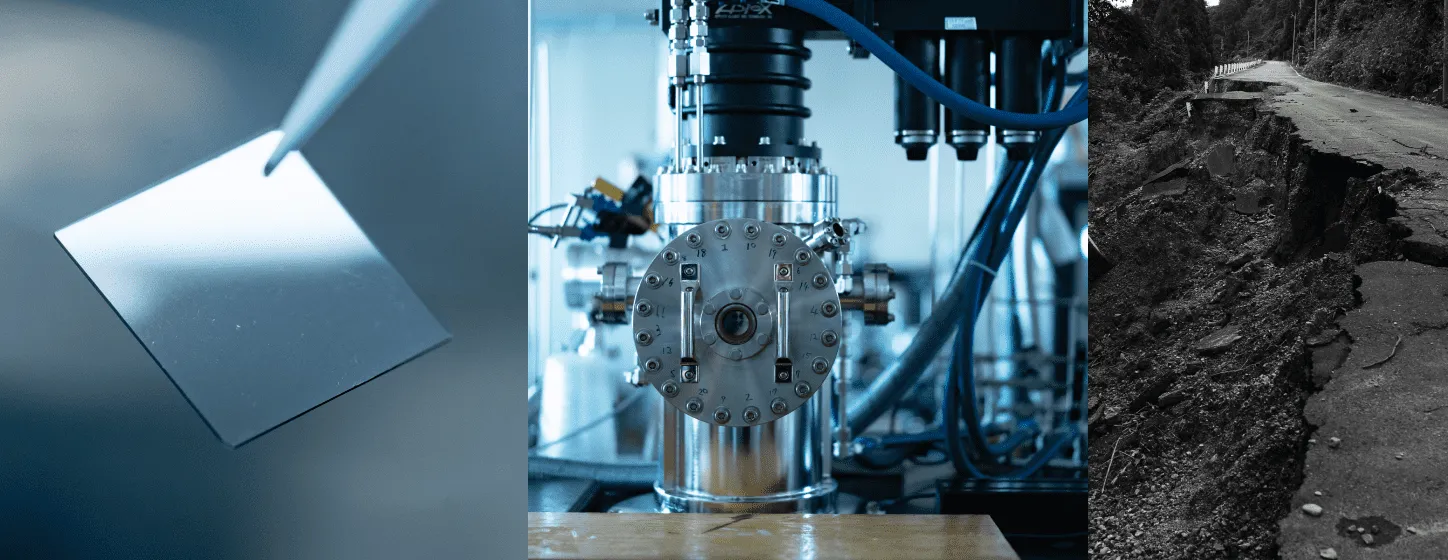
2011.3.11~
東日本大震災と福島第一原発事故
分散していた技術・知見が一か所に
廃炉に向けた明確な使命が、開発を急激に加速
福島第一原子力発電所の事故を契機に、ダイヤモンド半導体の実用化への道程は一気に加速していく。
廃炉に向けて燃料デブリを取り出す、という世界でも前例のない困難なミッションが生まれる中、ダイヤモンド半導体の「放射線量の高い過酷な環境でも壊れない」という特性に一気に注目が集まった。事故の翌年2012年にはダイヤモンド半導体の開発に挑む国家プロジェクトがスタート。
本プロジェクトは、日本原子力研究開発機構(JAEA)が主催。産総研や北海道大学、高エネルギー加速器研究機構(KEK)などが参画し、共同創業者である星川と金子、梅沢がチームを組むきっかけになった。
過酷環境に耐えられる半導体が必須、という強い認識の元、ダイヤモンド半導体は国需として求められる存在となったため、各研究機関がそれぞれ保有し分散していた、ダイヤモンド半導体の技術ノウハウを集約することができた。
本プロジェクトは、日本原子力研究開発機構(JAEA)が主催。産総研や北海道大学、高エネルギー加速器研究機構(KEK)などが参画し、共同創業者である星川と金子、梅沢がチームを組むきっかけになった。
過酷環境に耐えられる半導体が必須、という強い認識の元、ダイヤモンド半導体は国需として求められる存在となったため、各研究機関がそれぞれ保有し分散していた、ダイヤモンド半導体の技術ノウハウを集約することができた。

2022~
大熊ダイヤモンドデバイス創業
結集した国内の英知を具現化するため、
大熊ダイヤモンドデバイス創業
廃炉という国難に立ち向かうため、国内の英知が結集したことにより、2021年にはダイヤモンド半導体によるアンプ試作品が世界で初めて完成。10年間にわたる共同研究は大きな成果を見せた。しかしながら、ダイヤモンド半導体の製品製造・量産化体制を担える組織がなく、廃炉への応用はまた課題が積み上がった。
手詰まりの状況を打破するため立ち上がったのが、大熊ダイヤモンドデバイス代表取締役の星川である。星川は、北海道大学発学生ベンチャーとして在学中より起業し、他分野で連続起業家として活躍。2016年には金子研究室と出会い、廃炉プロジェクトの内容とダイヤモンド半導体の将来性に共感。使命感に駆られ、自ら志願しプロジェクトの立ち上げ時から製品化担当として事業統括管理業務を行ってきた。
そして星川と共に創業者となったのは、北海道大学の准教授であり、事故後はJAEA廃炉国際共同研究センターグループリーダー(当時)を兼任し、これまで廃炉の使命を担ってきた金子。そして産総研で上級主任研究員を務め、ダイヤモンド半導体の世界的権威である梅沢だ。
この3名が中心となり、ダイヤモンド半導体デバイスの商用化・量産化を担う組織として、2022年に大熊ダイヤモンドデバイス株式会社が創業した。
手詰まりの状況を打破するため立ち上がったのが、大熊ダイヤモンドデバイス代表取締役の星川である。星川は、北海道大学発学生ベンチャーとして在学中より起業し、他分野で連続起業家として活躍。2016年には金子研究室と出会い、廃炉プロジェクトの内容とダイヤモンド半導体の将来性に共感。使命感に駆られ、自ら志願しプロジェクトの立ち上げ時から製品化担当として事業統括管理業務を行ってきた。
そして星川と共に創業者となったのは、北海道大学の准教授であり、事故後はJAEA廃炉国際共同研究センターグループリーダー(当時)を兼任し、これまで廃炉の使命を担ってきた金子。そして産総研で上級主任研究員を務め、ダイヤモンド半導体の世界的権威である梅沢だ。
この3名が中心となり、ダイヤモンド半導体デバイスの商用化・量産化を担う組織として、2022年に大熊ダイヤモンドデバイス株式会社が創業した。

WHAT’S NEXT
社会実装に向けた現在地
創業前より培った圧倒的な技術優位性を土台に、
福島県大熊町に世界初となる
ダイヤモンド半導体工場を建設
大熊ダイヤモンドデバイスは、創業前からの10年以上繰り返した試行錯誤の結果、世界で唯一の垂直統合ノウハウを構築。それによりラボスケールで90%以上の歩留まり※も実現した。また、廃炉という至上命題に取り組んだ10年間は、研究開発だけでなく、ダイヤモンド半導体を求める市場との対話を生み出し、実用化への道のりを加速させることとなった。
日本特有の課題である廃炉に対して10年以上向き合った結果、少なくとも今後数年以上にわたる圧倒的な技術優位性を確立し、工場の建設に手が届く世界で唯一の存在となった大熊ダイヤモンドデバイス。創業使命を果たすため、世界初のダイヤモンド半導体工場は、福島第一原発のある福島県双葉郡大熊町に建設中。2026年の竣工を目指している。この使命は、大熊ダイヤモンドデバイスに更なる技術優位性をもたらすと共に、今後日本発の次世代半導体産業を創造していく上で確かな基盤となるだろう。
日本特有の課題である廃炉に対して10年以上向き合った結果、少なくとも今後数年以上にわたる圧倒的な技術優位性を確立し、工場の建設に手が届く世界で唯一の存在となった大熊ダイヤモンドデバイス。創業使命を果たすため、世界初のダイヤモンド半導体工場は、福島第一原発のある福島県双葉郡大熊町に建設中。2026年の竣工を目指している。この使命は、大熊ダイヤモンドデバイスに更なる技術優位性をもたらすと共に、今後日本発の次世代半導体産業を創造していく上で確かな基盤となるだろう。
※製造したトランジスタのうち動作が確認できた割合

OUR VISION
ダイヤモンド半導体が拓く未来
次世代インフラ構築に寄与し、
人類の歴史を一歩前進させる
ダイヤモンド半導体の可能性は、廃炉への貢献だけに留まらない。高温/低温や放射線といった過酷環境に耐えられるだけでなく、優れた高周波・高出力性能・大電力効率を持つため、原発、宇宙産業、次世代通信産業といった近年の社会課題の解決に有用だ。
さらに既存の半導体技術では実現困難なレベルの省電力特性を持ち、脱炭素社会の実現に大きく寄与することができる。通信衛星の更なる進化や次世代通信技術の実現など、ダイヤモンド半導体は次世代情報社会のインフラを支える存在として期待されている。
我々が考える真の意味での復興とは、原発事故というマイナスをゼロにするだけではない。そこから新たな産業を生み出し、プラスに転換していくことにある。ダイヤモンド半導体を活用して原発事故を乗り越え、それによって集積した技術によって人類がさらに一歩先に進む。これこそ、私たちが目指す未来だ。私たちは、福島第一原発の廃炉実現を通じて、日本発の次世代半導体産業を創造していく。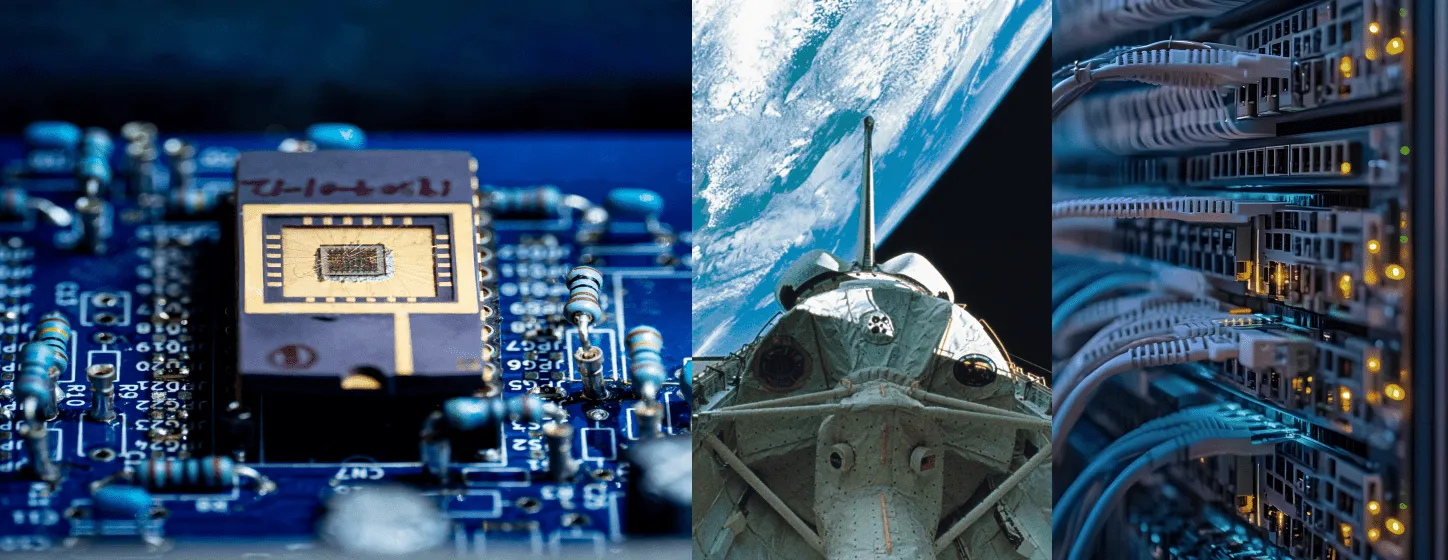
さらに既存の半導体技術では実現困難なレベルの省電力特性を持ち、脱炭素社会の実現に大きく寄与することができる。通信衛星の更なる進化や次世代通信技術の実現など、ダイヤモンド半導体は次世代情報社会のインフラを支える存在として期待されている。
我々が考える真の意味での復興とは、原発事故というマイナスをゼロにするだけではない。そこから新たな産業を生み出し、プラスに転換していくことにある。ダイヤモンド半導体を活用して原発事故を乗り越え、それによって集積した技術によって人類がさらに一歩先に進む。これこそ、私たちが目指す未来だ。私たちは、福島第一原発の廃炉実現を通じて、日本発の次世代半導体産業を創造していく。